「刺さる/伝わるメッセージ」を生み出す、デザイン目線の発想法
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コメント
ただいまコメントを受けつけておりません。
「刺さる/伝わるメッセージ」を生み出す、デザイン目線の発想法

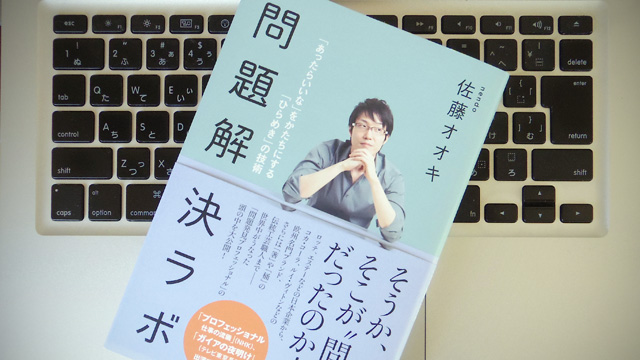
『問題解決ラボ――「あったらいいな」をかたちにする「ひらめき」の技術』(佐藤オオキ著、ダイヤモンド社)は、300以上の案件を同時進行で解決しつづけるデザイナーである著者が、「すでにそこにある答え」に気づくための「正しい問い」の見つけ方を紹介した書籍。
その冒頭、「はじめに『デザイン目線』で考えると、ホントの課題が見えてくる」には、こんな記述があります。
重要なのはデザインのジャンルではなく、新しい視点を提供することでいかにして目の前の問題を解決できるか、です。(中略)こうした新しい視点での問題解決に必要なものこそ、「デザイン目線」で考える、ということ。今までさんざん悩んでいた問題には全然違う側面があると気づくことができ、アイデアが「詰まり」なく出てくる体質になり、問題解決の新しい筋道が見つかって……と、真の課題、本当の答えにたどり着くことができるようになります。
重要なのは、「デザイン目線」はデザイナーだけができる特殊なスキルではないということだとか。本書ではそんな視点に基づき、「問題発見」「アイデア量産」「問題解決」「伝え方」「デザイン」についての考え方を提示しているわけです。なお、個人的には、各本文のあとについているコラムにこそ、多くの人が応用できそうなヒントが隠れていそうだと感じました。
そこできょうは、第4章「デザイン目線で考えると、刺さる『メッセージ』が見えて来る オオキ流『伝え方』講座」のコラムに焦点を当ててみましょう。
メッセージはぎりぎりまで絞り込む
誰の目線でメッセージを伝えるかは、とても大事なこと。しかし、多くのメッセージは「ピント」が合っておらず、ピントが合っていないメッセージの多くは、「盛り込みすぎ」だといいます。幕の内弁当のように、バランスよくいろいろ盛り込む方が安心感があるのかもしれないけれども、メッセージは研ぎ澄ましていった方が刺さるということ。
だから、言いたいことがたくさんあっても、メッセージに優先順位をつける。そのうえで、優先順位の低いものは、思い切って捨てる。そうすることによって伝えたいことの核心がより際立ち、深く刺さるメッセージを発するアイデアが生まれるというわけです。(146ページより)
「ほどく」作業ですでにあるモノを棚卸し
「すでにある」技術やモノを転用する際、やってはいけないのは、「こういうものをつくりたい」という感じで乗り込んでいくことだそうです。…
