社会
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
新潟水俣病、国の責任認めず=3次訴訟、原因企業に賠償命令―地裁
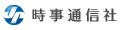
新潟水俣病の未認定患者ら11人が国と新潟県、原因企業の昭和電工を相手に1人1200万円の損害賠償などを求めた第3次訴訟の判決が23日、新潟地裁であった。大竹優子裁判長は昭和電工に一部原告への賠償を命じたが、国と県への請求は棄却した。
新潟水俣病をめぐる判決は1992年の第2次訴訟第1陣の判決以来、23年ぶり。過去の判決でも国の責任は認められていなかった。
訴状などによると、原告は新潟市と同県阿賀野市で出生した40〜80代の男女で、工場排水に含まれるメチル水銀に汚染された阿賀野川の魚介類を食べたことにより、手足のしびれやめまいなどの症状が出ていると主張。工場排水を長年排出し続けた昭和電工に加え、国や県は排水を規制するなど水俣病の発生、拡大を防止する義務を怠ったと訴えていた。
国や県などは「症状は他の病気に起因するもので、水俣病とは言えない」などと主張していた。
PR -
三島の東京五輪取材ノート=全集未収録の全58ページ発見
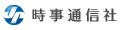
昭和期を代表する作家の三島由紀夫(1925〜70年)が、64年の東京五輪を取材したノートが見つかり、23日までに発売された雑誌に内容が掲載された。選手のリアルな表情が生き生きと具体的に描かれ、三島の取材記者としての意外な一面がうかがえる。
三島は朝日、毎日新聞などの特派記者として五輪を取材。寄稿記事は全集にも収録されたが、ノートの全体像は分かっていなかった。
ノートには10月10日の開会式から各競技の模様、同24日の閉会式までを58ページにわたり記録。重量挙げで金メダルを獲得した三宅義信選手については「上げる前に、両手をつかへ天を仰ぎ、口をモグ※(※=くの字点)させる。更に上を仰ぎアウッと叫ぶ」と生々しく描写されている。
三島由紀夫文学館を運営する山梨県山中湖村が遺族より入手した資料から発見。佐藤秀明近畿大教授らが確認を進め、全文を研究誌「三島由紀夫研究(15)」に掲載した。実物は24日から同館で展示する。
文芸評論家の松本徹同館館長は「三島に国粋主義的な態度が現れていた時期だが、それが全く出てこない。日本を代表する作家として、国際的視野に立ち表現しようとした姿勢がうかがえる」と話している。
-
製品使用者らへの賠償認めず=石綿訴訟、遺族側敗訴―神戸地裁
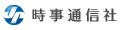
大手機械メーカー「クボタ」の旧神崎工場(兵庫県尼崎市)に出入りしていた運送業者と、アスベスト(石綿)入り耐熱製品を使っていた溶接工の2人が肺がんで死亡したのは石綿が原因として、遺族が同社と国に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁(松井千鶴子裁判長)は23日、原告側の請求を棄却した。
-
グローバルCOEプログラムの事後評価、北大など5大学が最高評価

文部科学省は3月19日、「グローバルCOEプログラム」(平成21年度採択拠点)の事後評価結果を公表した。9拠点のうち、北海道大学、東京工業大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学の5拠点が最高評価を得た。
同プログラムは、大学院の教育研究機能を一層充実・強化するため、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点的に支援する事業。今回の事後評価は、平成21年度に採択され、5年間の補助期間を終了した9大学9拠点を対象としている。
各大学から提出された事業結果報告書などについて、書面、ヒアリング、現地調査により調査・分析し、4段階で総括評価。9拠点のうち、北海道大学、東京工業大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学の5拠点が、4段階でもっとも高い「設定された目的は十分に達成された」と評価された。
残り4拠点の東京大学、京都大学、東京女子医科大学、早稲田大学は、4段階中2番目によい「設定された目的は概ね達成された」と評価された。「ある程度達成された」「あまり達成できなかった」と評価された拠点はなかった。
プログラム全体としては、「目的に沿って、概ね順調に実施されたと言える」と評価。具体的には、大学の将来構想策定、国際機関や海外大学との協力協定締結、人材育成などの成果があったという。
なお、事後評価やプログラム内容の詳細については、日本学術振興会がホームページで紹介している。 -
神奈川県教委、小中一貫モデル校10校を指定

神奈川県教育委員会は3月20日、平成27年度小中一貫教育モデル校を発表した。モデル校として、海老名市の有馬中学校など10校を指定。モデル校は、地域や児童生徒の実態を踏まえながら実践研究に取り組む。
学識経験者や学校関係者を構成員とする「小中一貫教育校の在り方検討会議」が、平成27年2月に取りまとめた一次報告を踏まえて、平成27年度小中一貫教育モデル校を指定した。指定期間は平成27年4月1日~平成28年3月31日。指定は年度ごとに行い、更新する場合は初年度を含め2年間を上限とする。
平成27年度小中一貫教育モデル校は、海老名市(有馬中学校区)の有馬中学校と有馬小学校、門沢橋小学校、社家小学校の4校、秦野市(北中学校区)の北中学校と北小学校の2校、箱根町(箱根中学校区)の箱根中学校と湯本小学校、仙石原小学校、箱根の森小学校の4校、合計10校。
モデル校は、地域や児童・生徒の実態を踏まえながら「期待する成果」や「解決を図りたい課題」などの重点を明確にしたうえで実践研究に取り組む。その取組みについては、成果と課題を整理・検証し、県内に普及する。
